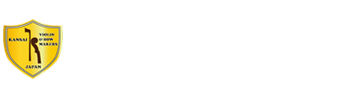努力と運、そして心のむずむず

成功はすべて運によるものだ――少なくとも、哲学者ギャレン・ストローソンの考えに従うならば。
人間は完全に自由な選択をすることができない、と彼は言う。何かを成し遂げたとしても、それは結局のところ運がよかっただけなのだ。
親が裕福だったから成功した、いわゆる「親ガチャ」の話なら、まだ納得しやすい。だが、この話はもっと奥が深い。彼が言うのは、生まれ育った環境の話だけではない。能力や性格、その他もろもろの要素もまた、すべて運によって決まるのだ。
10kgのダイエットに成功した?運よく、痩せやすい体質だったのかもしれない。がんばってランニングを続けた?運よく、ランニングが楽しくなったからかもしれない。糖質制限もして、タンパク質をたくさん摂った?いや、たまたま、プロテインバーが自分の好みにぴったりだったからかもしれない。
こうなると、恵まれない環境に生まれながらも、貧困に耐え、涙ぐましい努力の末に大成を遂げた偉人ですら、「運がよかった」の一言で片付けられてしまう。お金がなくとも、たまたま頭が良かったのかもしれない。あるいは、人一倍努力して学び、成功をつかんだのだとしても、それすら「運よく努力できる性格だったから」と言えてしまう。
もちろん、自分が現在バイオリン作りを仕事として生活できているのも、たまたま運がよかっただけということになる。
そう言われると、どこか手の届かないところがむず痒くなるようで、どうにも落ち着かない。なぜだろう。
「努力は報われる」――幼いころから繰り返し聞かされてきた言葉があるからだ。
子どものころは前向きな響きに勇気づけられるものの、やがてその実態のない甘さに気づき、もどかしさを覚えるようになる。努力しなくても成功を手にする人がいる一方で、どれほど尽力して
も報われる気配すらない人もいる。そして、成果の有無にかかわらず挑戦し続ける人もいれば、途中で足を止める人もいることを、周囲の人々や社会の現実を見ながら、少しずつ理解していく。
そうしているうちに、努力と成果の関係だけでなく、「運」という不確かな要素についても考えざるを得なくなる。だから、多くの大人は「すべては運だ」と言われても、なんとなくそうかもしれないと思うことはあっても、完全に否定はできない。ただ、「頑張ればできる」という刷り込みがあるせいで、素直に肯定することも難しい。そうして、心のどこかがむずむずし始める。
過去の成功を振り返りながら「運」の影響を考えすぎると、自信が揺らぐ。自分の実力が本物な
のか、不安になってしまうからだ。逆に、未来のことを考えると、どれだけの要素が自分のコントロールを超えているのかを思い知らされ、怖くなる。
人は何事でもコントロールしたくなる。そして、運とは、自分の力ではどうにもできない要素のことを指す。だから「運」について考えすぎると不安になったり怖くなってしまったりする。特定の技術を身につけることで運の影響を減らすことはできるが、実際には、ある分野での実力が上がるにつれ、逆に運が結果を左右する度合いも増してしまうことがある。
だからこそ、大切なのは「すべてを支配しようとしないこと」なのかもしれない。運の影響を完全に排除することはできない以上、偶然を受け入れ、「よし、これでいい」と思える心の余裕が持てるかどうかが鍵になる。
創作活動では、偶然のひらめきや思いがけない要素が加わることで、作品がより深みを増し、魅力的なものへと進化する。それは演奏家にとっても、楽器を作る職人にとっても同じだ。
最初から最後まで完璧にコントロールされた作品は、技術の高さに驚嘆することはあっても、心を揺さぶられることは少ない。むしろ、運という要素を受け入れた、どこか不完全なもののほうが、人の感情を強く動かすことができるのだ。
完璧な人間など存在しない。それでも、あなたの心を動かした誰かがきっといたはずだ。バイオリンも、音楽も、結局はそういうものなのだろう。
生きることは、無数の分かれ道がある長い道を歩きながら、並んだ箱を一つずつ選びながら開けていくようなものだ。開けるまで中身は分からない。運よく美味しいケーキが入っていることもあれば、思いがけず蛇が潜んでいることもある。だが、どの箱も決して空ではない。それぞれに何かし
らの驚きが詰まっており、必ず得るものがあるのだ。
だからこそ、今の状況にとらわれて自分の運のなさを嘆く必要はないし、成功したのは全てラッキーだったからですよと卑屈になる必要もない。開けなかった箱の中身が何だったのかを知るす
べはなく、それを気にしても意味がないのだから。