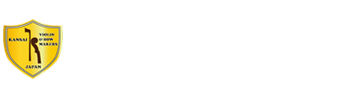ヴァイオリンの調整
私は今年83歳、引退する時期かとも思うが、展示会での若い製作者や来場者との交流、来店して頼りにしてくれる人たちや新作ができるのを楽しみにして試奏・評価してくれるヴァイオリンの先生に支えられて、今年も大阪の中之島公会堂での展示会に出品する予定です。
今回は、日ごろのヴァイオリンの修理や調整を通じて感じていることで、弾く人が日ごろの扱いで知っていて役に立つと思われる基本的なことを、書くことにしました。
自然の木で作られているので、複雑な部品で組み立てられたヴァイオリンの木の変化は、音色や弾き易さに大きな影響を与えます。
A: 環境の変化(温度・湿度)
B: 経年変化(含水量・繊維の結晶化)
C: 長年弾きこむことにより、奏者のスタイルに合わせて音色が変化
A・Bの場合は形状が変化(膨張または収縮)するので、魂柱や駒の調整または交換が必要になる。最悪の場合は割れが発生することもある。
C は、人が身に着けるものが日ごとに馴染んでくるように、ヴァイオリンも弾きこむことにより、音色のコントロールが容易になり、響きも良くなると言
われており、このようなヴァイオリンを別の人がいきなり弾いてもコントロールが難しい。
魂柱や駒は小さな部品であるが、弦の振動を表板・裏板に伝えるキーになる部品で、共に接着されず挟まれた状態で取り付けられており可動である。その形状と取付位置により各々の弦の音色やバランスが決定される。
駒の形状(形・厚み)については、より良い音色を求めて、また音色に関する問題解決のために、いろいろ興味ある試行錯誤の結果が学会誌に報告されているほどである。
通常、駒や魂柱の位置は標準的な位置に設定されている。0.5mm移動するだけで音色が変化するので、弾く人が音色にこだわりがある場合は、音色とバランスを確認しながらそのヴァイオリンの最良の位置を探る、弾く人と調整者との掛け合いの微妙な調整作業が必要である。